ドゥルーズ: 2013年3月 Archives
うむ。フーコーらしいですね。1971年チュニスで行われたものらしい。2011年に「ワシントンナショナル・ギャラリー展」で僕は本書にフーコーがとりあげた「鉄道」と「オペラ座の仮面舞踏会」をじっくりとみている。読んでいて臨場感で眠れなくなりそうだった。それでも草稿を破棄したのであれば、フーコーには何か「ひっかかり」があったのかもしれない。そう、これはマネを自分にひきつけるフーコーにしかやれない「分析」だ。読んで数時間後の「感想」だから、この記事は削除するかもしれない・・。

(NEX-7/E2.8/16_PL/SILKYPIX)
『マネの絵画』で論じられた当の絵をPDFでここにまとめてあります。AcrobatでプレスPDF向けに作成してますのファイルサイズが大です。50-60%でごらんになってください。
1989年の初頭、ささやかな本が刊行された。『コレージュ・ド・フランス年鑑』のためにフーコーが記した《講義概要》を、それは集めている。彼が書いた最後の概要は、《主体の解釈学》に当てられた、1981~82年度の講義にかんするものである。その末尾には、ストア派の教えにかんする以下の言及を読むことができる。
「死にかんする瞑想の独得の価値が生み出されるのは、世論では一般に最大の不幸と考えられている事態を、その瞑想があらかじめ思索するからだけではないし、また、その瞑想のおかげで、死は不幸にあらずということを確信できるからだけではない。自分の人生にたいして回顧の視線を、いわば先取りの思索によって投じうる可能性を、その瞑想こそが提供してくれるのである。自分は死に瀕しているのだと自分自身のことを考えることによって、われわれは現に自分が行ないつつある行為の一つ一つをそれ独自の価値において評価することができる。エピクテトスの言うところによると、死は農夫をその耕作中に、船乗りをその航海中に襲うのであって、〝ところできみは、何をなしているときに死に襲われたいのか?〟というわけである。そしてセネカは死の瞬間をば、人が自分自身の言わば審判者となりうる、そして、自分の最後の日までに達成した道徳的進歩を測りうる、そうした瞬間だと見なしていた。セネカは第二十六書簡のなかに、こう書いていた、〝私がなしうる遺徳的進歩については、私は死を信じよう…。私は自分が自分自身の審判者となるであろう日を、そして徳を自分が口の端にか、それとも心のなかにもっているかを知るであろう日を、待っている〟」。 これらのいくつかの文章は、何と不思議な木霊を今日ひびきわたらせていることか。(引用終わり)
(シャシンは本文とは関係ありません)

(NEX-7/E16mm F2.8 /Photoshop CS)
以下は河出文庫版(宮林寛 訳)ドゥルーズ『記号と事件』P277です。
教師の実生活が面白いということはまずありえません。もちろん、旅をすることはあります。ですが、教師は言葉や経験によって旅費をまかなうわけで、学術会議や討論会に出席し、いつも、ひっきりなしにしゃべっていなければならないのです。知識人は膨大な教養を身につけていて、どんなことについてでも見解を述べる。私は知識人ではありません。すぐに役立つような教養もないし、知識の蓄えももちあわせていませんからね。私が何かを知っているとすれば、それは当座の仕事の必要上知っているだけなのであって、何年もたってから過去の仕事にもどってみると、一切を学びなおさなければならなくなっているほどです。かくかくしかじかの点について見解も考えももたないというのはとても気持ちがいい。私たちはコミュニケーションの断絶に悩んでいるのではなく、逆に、たいして言うべきこともないのに意見を述べるよう強制する力がたくさんあるから悩んでいるのです。旅をするとは、出かけた先で何かを言ったかと思うと、また何かを言うために戻ってくることにすぎない。行ったきり帰ってこないか、旅先に小屋でも建てて住むのであれば話は別ですけどね。だから、私はとても旅をする気になれない。生成変化を乱したくなければ、動きすぎないようにこころがけなければならないのです。トインビーの言葉に感銘を受けたことがあります。「ノマドとは、動かない人たちのことである。旅立つことを拒むからこそ、彼らはノマドになるのだ」というのがそれです。(引用終り)
最近何度か「線」のことを記事にしている。それで、ドゥルーズが「点は嫌い」ということをどこかで言ってるその箇所を探しているのです。が、なかなか見つからない。その探索の折にこれに「再会」したというわけです。ココは僕が大変気に入ってる箇所です。「人には旅をする必然性はない」という僕の妙な信念の根拠になってます。セックス(性行動)と同様「旅」にも必然性はない、というような意味ですがね。ww。
ドゥルーズのこの言は1988年、ちょうど僕の今の年齢なのです。読み手はかくのごとく何度もなんども行き着くのです。それにしても「点は嫌い」の典拠はどこにいったのでしょうか?
中空にサザンの歌が響くなか三年一組四十回跳ぶ
「みんなでジャンプ」という詞書が添えられてあるから、体育祭での縄跳びの種目なのだろう。体育祭に合うサザンの歌ってなんだろう? アップテンポで乗りのいい曲なんだろね。これもまた20年以上も前のハナシだ。
さて。「フロントランナー」の桑田 佳祐。食道がんから復帰してきた。(拡大画像アリ)
(NEX-7/E16mm F2.8 SEL16F28/SILKYPIX)
(以下は記事から)―日本語に対する思いが深まってきたのはなぜですか。
やっぱり、自分の『血』とか本音をリアルに歌えるのは日本語なんです。外人のマネばっかりじゃラチがあかない。新曲に対する褒め言葉として「いいメロディーですね」っていうのはあんまりなくて、「歌詞のこの部分が好き」っていうのが多い気がします。
昔は妙に潔癖で、メロディーに対して歌詞があふれてしまう字余りがイヤだった。でも、自分が気にしているほど周りは気にしてない。ライブやテレビ番組で、岡林信康さんとか浅川マキさんの曲をカバーするなかで、多少は字余りでも聴いてくれる人の許容範囲なんだ、もうちょっと白由になっていいんだと思えた。しょうがない時は音符の数を増やせばいい。50歳過ぎてわかってきましたね。
(引用終り)ふむふむ。桑田 佳祐の「生成」として考えてみる。出来事とか事件とかいうものはこのようなものではないか、と。これはやはり「点」ではなく「線」とみる。桑田 佳祐の数々の線が交差したところに「点」を指示することはできても、指したとたんに逃げて(消えて)ゆく。桑田 佳祐はこのようになったのだ・・。これを「日本回帰」といわずにおきましょう。「年齢」とか「日本人」とかいうことがいわゆる「主体化のプロセス」の問題とどのように関係するのか、正直僕はわからないでいる。フランス人には当たり前でも日本人にはどっこいそうはゆかない、ってことがあるのかも知れない。同じように若いときにはなかった情緒や論理が歳をとるとあらわれてくる、ということもあるのかもしれない。「年齢」とともに変異する様態、「日本人」としての属性、そういうことは当然あるでしょうから・・。
「禅」には「主体化」を消去するようなところがある・・というようなことをフーコーだかドゥルーズだかに(あるいは双方に)読んだ記憶がある。やはり(はたして)そうなのだろうか? それほどたやすく「主体化」を阻めるものでしょうか? 禅の「主人公」というのは「主体化」のことではあるまいか。日本浪漫派閥的日本人!(なによそれ)にだってフランスの現代思想的「主体化」はあるのです、と思いたい・・。
D・エリボンの『ミシェル・フーコー伝』(新潮社・田村訳)。P182-183。デリダとフーコーの確執の場面。日本人にはこんなことはまずないでしょうね。フランス人はこうなのでしょう。40代半ばのフーコーですが、デリダに対する容赦なき批判には感情的な面があるが、それゆえにこそ光る真実(あるいは真実味)がある。フーコーはこうなのでしょう。彼こそは「ピカレスク」なのだ。そこに彼の魅力もある。
/////////////////////////////////////////////////////////
しかし、いさかいは起こった。ただし事後に起こったのだ。いかなる理由でか? それを知ることはかなり難しい。それまではかなり限られた聴衆にしか当てられていなかったこの講演が、一冊の本のなかに再録されたのを見て、同日とうとうフーコーは腹を立てたのか? 何人かの人が、ある推測をしている。フーコーの突然の態度の変化と思われるものを説明できるのはこの推測だけであるとは決定しないまま、しばらくこの推測につきあってみよう。
『エクリチュールと差異』が出版されたとき、フーコーとデリダはどちらも『クリチック』誌の編集委員会のメンバーだった。デリダのこの本についてのジェラール・グラネルによる論文が編集部に届いたが、これはデリダへの賛辞に満ちているものの、フーコーへの嫌味がいっぱいあった。フーコーはこれに怒り、デリダにこの論文を載せないように頼んだ。デリダは編集委員会の一員として、自分に関係のある論文については口出ししないよう望んで、この介入を拒絶した。論文は掲載される。と、時を置かずにフーコーはデリダが一九六三年に行なった前述の講演にこたえる、非常に激烈な論文をしたためた。
フーコーが一九七一年に『パイディア』誌に《私の身体、この紙、この炉》という表題で載せた返答がこれである。これは一九七二年の『狂気の歴史』増補版の末尾に再録される。フーコーはこの増補版を「返事が非常に遅れてしまってすまない」という献辞とともにデリダに送った。九年の遅れである! フーコーの、このテクストの結びには、あたかも宣戦布告のごとき響きがある。役割がひっくり返ってしまって、今度は師がかつての弟子を断罪するのである。
すなわち、「が、少なくとも一つの事柄にかんしては私は同意見である――古典的解釈者たちがデカルトのそのくだりを、デリダ以前に、しかも彼のように消し去ったのは、彼らの不注意のせいではまったくない、という事柄については。それは計画的な仕組によるものである。今日デリダがもっとも決定的で、最後の輝きのなかにある代表者となっているその仕組。すなわち、言説中心の実践をテクスト中心の痕跡へ還元すること、読み方にとってのいくつかの特徴だけに留意するため、その実践で生じている出来事を省略すること、言説への主体の包含関係の様式を分析しなくてもすむように、テクストの背後に、ある声を考案すること、起源にあるものを、テクストのなかで述べられることと述べられないこととして規定し、言説中心の実践を、それがおこなわれる変容の場にふたたび位置づけしないこと。」
そしてフーコーは、次のような最終的判断を下している。「それは一つの形而上学だ、言説中心の実践のこうした《テクスト化》に隠される形而上学一般、ないしそれの閉じ込めだ、なぞと私は言おうとするのではない。もっと徹底して私はこう言いたいのである。それはきわめて可視的な仕方で明らかになっている、歴史的にはつきり想定れたささやかな教育である、と。子供に向かって、テクストのほかには何も存在しない、[・・・]と教えこむ教育。際限なくテクストを再読することを可能にする無限のあの権威を教師の声に与える教育である。」
ここでデリダの《脱構築》は、伝統ならびに権威の《復元》活動へと送り返されている。文筆の共和国では、フェンシングの剣先にたんぽをつけて闘われたりはしないのだ。この時から、このふたりの掌者のあいだの断絶は、全面的で絶対的で根本的なものとなり、しかもおよそ十年近くつづくだろう。ふたたび両者のあいだに繋がりがうち立てられるためには、一九八一年プラハで、反体制派によって組織されたセミナーに参加しようとして出向いたデリダが《麻薬所持》で逮捕される事件が必要となる。フランスでの衝撃は大変なもので、政府筋がチェコ当局に働きかける一方、フランス知識人のあいだでも抗議の呼びかけが広まった。フーコーはまっさきにこれに署名したうちのひとりであったし、デリダの行動を支持するためにラジオで語ったりもする。デリダは数日後パリに帰ると、フーコーにお礼の電話をした。それからは彼らはいろいろな機会に顔をあわせる。
/////////////////////////////////////////////////////////
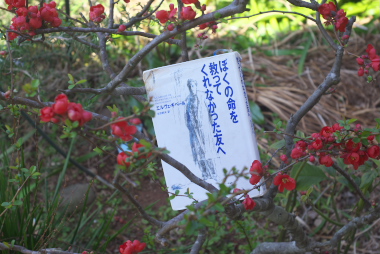
(NEX-7/Elmar f=5cm 1:3,5)
ここんところずっとフーコーを読んでいた。その合間にエルヴェ・ギベールを読む。同書を知ってはいたが読まないでいた。で、読後の感想。後味はよくなかった。『ぼくの命を救ってくれなかった友へ』という書は「功罪アリ」と感ずる。どこまでが真実でどこまでがギベールの物語なのかわからない。救いがない。それでも、フーコーのモデルとされる男は用意周到に「自己の技法」を貫いた印象がする。ミュージル(フーコーのモデルとされる人物)の最後は「芸術作品」で、皮肉にもギベールを拒んでいるようにも思える。
医療機関の中でひとつの骸(むくろ)となったフーコー。その中に入れば患者と医師という奇妙で独特の権力関係にはいり、処置されるしかない患者フーコー。特別な権力がどのようにして現在のようになったのか、その歴史的・系譜的な研究をずっとしてきたフーコーが、その病院の中で死んだ。「頸部穿孔をうけたのである。額に孔をあけられた跡があった」とギベールは書いてある。(再度申しますが、それが真実かどうかわからない)
人はどのようなかたちであるにせよ、死ぬときはたったひとりで黄泉におもむく。僕だっていずれみなさんに「お先に失礼」ってことになる。それもそんなに遠いことではないはずだ。フーコーやドゥルーズの「孤独」を身近におもう。彼らが「権力」にあがらって(さらには利用もして)死んでいったすがたをおもう。フーコーの属性が僕の中にも分け持たれているとおもう。僕もまた新しいギリシャ人を発見し僕なりの実践をしたいとおもうが、そんな過激な力が僕にはあるだろうか?


